教育業界にもさまざまな仕事があります。今回は、中高生が放課後や休日にまちづくりに関わる機会をコーディネートしている、NPO法人らんたんの明楽香織(みょうらくかおり)さんをご紹介します。ご自身が子どもから大人になる過程で、人との関わり方が大きく変わり、それが今の仕事にも活きているそうです。
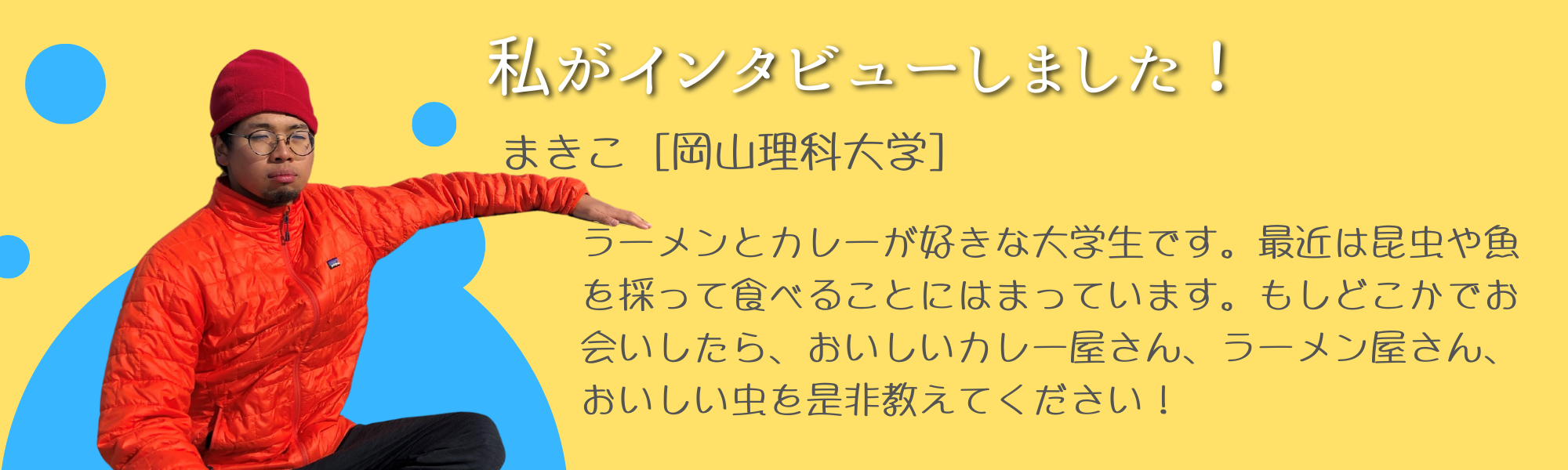
目次
明楽さんのこれまで
第1章 人と話すのが苦手だった子ども時代
――明楽さんはどんな子どもだったんでしょうか?

第2章 のめり込んだYMCAと成人式の実行委員会
――大学時代はどのように過ごしていたんでしょうか?

大学2年生のときは、岡山市の成人式の実行委員になりました。一つの企画をみんなで成し遂げることが楽しいなと実感したのは、成人式だったと思います。
――成人式の実行委員は立候補したんですか?

でも、YMCAの先輩で「成人式の実行委員はやりがいあったよ」と教えてくれる人がいて、参加しないといけないなら、実行委員でなら参加できるかなという気持ちで実行委員になったのを覚えています。

第3章 ももたろう未来塾と出会いで世界が広がった
――大学卒業後、YMCAで働く前に別の会社に就職されたんですね。

YMCAでお世話になっていた人に、仕事を辞めて帰ってきたと話をしたら、YMCAで人手が足りていないと言われて。YMCAのスタッフと小学校の特別支援学級の支援員を掛け持ちして、5年間働きました。
――YMCAの存在は明楽さんにとって大きいんですね。次のターニングポイントとして、28歳でももたろう未来塾に参加していますね。

――ももたろう未来塾はどのような場なんですか?

さらに、参加者はグループに分かれて、研究課題を設定して岡山県の課題について考えて、最後に「成果研究発表」として提言のような形にまとめます。わたしのグループは少子化がテーマだったので、小中学校でのキャリア教育のプログラムについて提言しました。
――どういった点が明楽さんにとってターニングポイントとなったんでしょうか?

仕事というと、たとえば教育分野だと学校の先生や学童の先生、大学の事務員ってイメージしやすいじゃないですか。わたしの仕事のイメージにはなかった、新たな事業を立ち上げたり、コーディネートをしたりするポジションも仕事になることを知れたのがももたろう未来塾でした。
――視野が広がったんですね。その後、30歳で地域おこし協力隊になるんですね。

YMCAは、平日は学童を運営して、土日にキャンプに行くといったスケジュールになっています。あまり器用ではないわたしは、YMCAの仕事と並行して新しい活動をすることが難しかったので、仕事を辞めました。
将来的に子どもが欲しかったので、自分の体のことを考えると30代前半が自由に動けるラストチャンスだなと思っていたんです。事務の仕事をするか、新しいことに挑戦するかを天秤にかけて、結構揺れたんです。自分にどんな力があるかわからないから、安定的な事務の仕事を続けた方がいいのかどうか、かなり迷いました。
――地域おこし協力隊という選択肢は、どういう経緯で出てきたんですか?

ももたろう未来塾に参加していたときに、久米南町役場から出向で来られていた方がいたんです。別の機会でその人に再会したんですが、その人がたまたま地域おこし協力隊の担当でした。
「今仕事していないんだったら、地域おこし協力隊になったらどう?ももたろう未来塾で話していたことが活きてくるかもよ」と言われて、まずは地域おこし協力隊のOBと話すことになりました。地域おこし協力隊になったのは、そのOBの方の影響が大きいですね。
第4章 教育へ舵を切る
――地域おこし協力隊になった当初から、具体的にやりたいことがあったのでしょうか?

けれど、マルシェのメニューを考えていても、子どもをイメージしたメニューを考えてしまったり、子どもたちの経験の場として何かできるんじゃないかと思ったりすることが多く、任期の途中から教育分野にも関わるようになりました。
そんななかで、教育に舵を切る出来事がありました。「未来商店街」という中高生が企画運営するイベントのコーディネートです。そして、久米南中学校の総合的な学習の時間で、生徒がフィールドワークに出るときのコーディネートも担当したことで、地域の教育に関わっていくことができるようになりました。
――地域おこし協力隊時代に特に印象に残ってることや、自分の成長を感じたことはありますか?

――ここまでお話を伺って、明楽さんの人物像が子ども時代と今とで変わったように感じます。それは今の教育の仕事にも繋がっているのでしょうか?

子どものころは自分自身が素を出せていなかったから、「小中学生のときに学校以外に立ち寄れる場所があったら、学校のメンバーとは違う人と出会える場所があったら、もっといろいろな人と話せていたんだろうな」と思うんです。だから、子どもたちにはいろいろな機会を掴んでもらいたいと思っています。

(編集:森分志学)






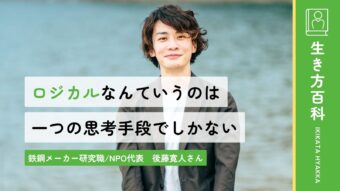



昔から運動が嫌いで、自由帳で絵を描くことが好きだったんです。小学1年生や2年生のころは、みんな長い休み時間は外に遊びに行くのに、わたしは教室にいました。そうしたら自然と距離ができていました。15歳までは本当に人と話さない子でしたが、高校は女子高に行って、同じ中学校の人が全然いなかったので、委員会活動をしたり学級委員になったりと、少しずついろいろなことに取り組んでいました。