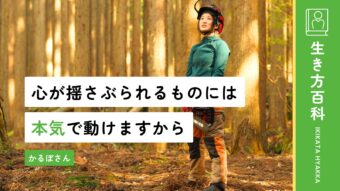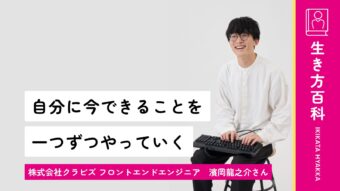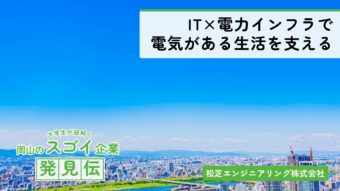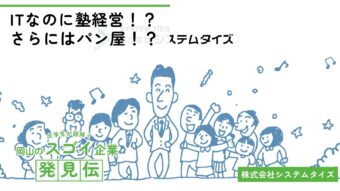思い描いていた「青春」とは少し違って、どこかモヤモヤを抱えて過ごしていた中高生時代。
それでも、小さい頃から好きだった「パソコンを触ること」や「イラストを描くこと」に夢中になる時間が、自分らしさを知る手がかりでした。
進学した専門学校の授業で偶然知った「アニメーション」の世界。その出会いをきっかけにプログラミングというスキルを武器に、試行錯誤を重ねながら、ものづくりに向き合ってきました。
「どうしたら、もっとおもしろくなるか」
常に問いかけながら、岡田さんは今も表現をアップデートし続けています。
目次
現在の岡田さんとこれまで
★岡田 隆志(おかだ たかし)さん
★松田さん

自分はもっとできるはずなのに


リモートでお仕事



前半はエンジニアの視点で、正しい技術を想定しているか、より良い実装方法や提案はないか、スケジュールに無理はないかなど、実際にプログラムを書く前段階で確認しながら進めます。
後半は、実際に手を動かして「モノを作りきる人」になるフェーズです。限られたスケジュールの中で、自分に出せる限りのクオリティを目指しながら毎回必死で取り組んでいます。


小学生の頃は、勉強も運動もそれなりにできて、人とのコミュニケーションも良好だったので、中学生になったらもっと楽しく青春を謳歌するイメージを持っていました。
でも、入学してしばらくすると、「あれ? 自分はもうちょっとできたはずなんだけどな……」とモヤモヤすることが増えるようになって。


何においても自信がなく、自己主張も苦手。「僕はこう思う」「みんなこうしようよ」なんて言えなくて、結局は人に合わせていたのだと思います。柔道部でも「なぜ負けるのか」を考えることさえせず、ただ辛い練習をこなすだけでした。
でも、プライベートでは昔からパソコンを触ったり、イラストを描いたりするのが好きで、そんな自分に自信を持っていることもありました。それを自分の軸として自信につなげられたら良かったのになと、今なら思います。



高校時代、柔道部の仲間と
パソコン×イラスト=デザインの専門学校へ








当時はまだ携帯電話がガラケーで、専門学校にもWEBサイト制作のコースがなかった時代。まだ珍しかったその授業に、僕はどハマりしました。「画面の中で何かが動く」ことがとにかくおもしろい。
ガラケーやデジカメで撮った動画を編集して、友達が作った曲に合わせてPV(プロモーションビデオ)を作ってみたり、当時あったFlash(フラッシュ)というアニメーションソフトを使って、自分で作ったホームページを動かしてみたり。
動画の”動き”そのものに感じる気持ちよさと、「次はこうなるのか」という動きの展開のおもしろさの中に、自分のテンションが上がるスイッチがあることに気づきました。さらに、それを人に見せた時にみんなが喜んでくれるというあの快感ーーデザインよりも、動画の方がずっと楽しかったんです。


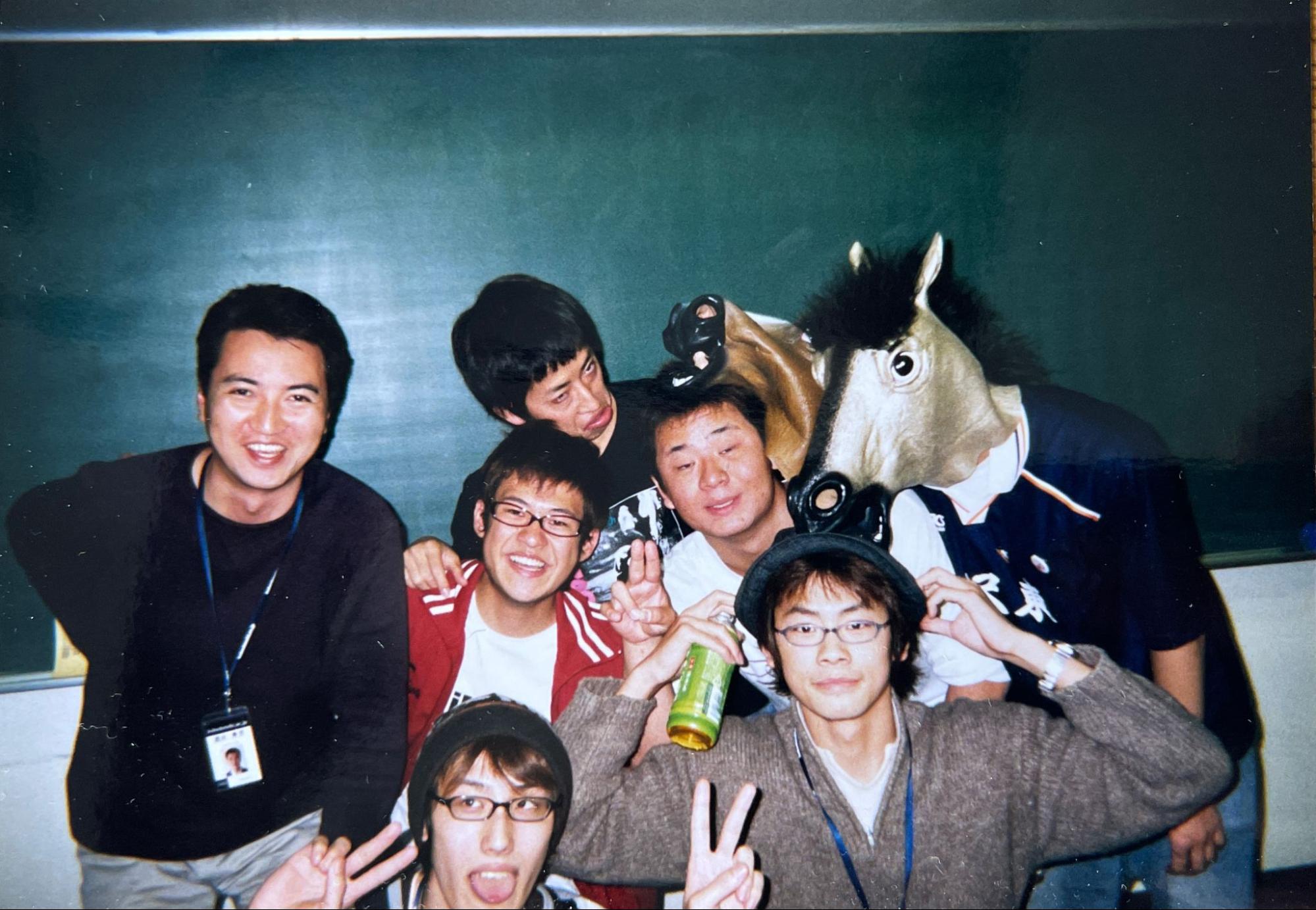
専門学校のクラスにて
ひたすら繰り返すことで、正解の境地へ




たとえば、動いていたロゴが停止するまでの時間が0.5秒なのか、0.8秒なのか。正直「どっちでもいいんじゃない?」と思いますよね。けれども、そのわずかな差でアニメーションの印象は大きく変わるんです。もちろん静止までの時間だけではなく、「スっと止まる」「ズーンと止まる」「スンっと行って戻る」のような「止まり方」にも数え切れないほどパターンがあります。
そんな細かな調整と選択を「俺は何をやってるんだろう」と思いながらも、何回も何回も何回も何回も、延々と繰り返してやり続ける。すると、あらゆる違和感がふっとなくなる瞬間が訪れて、「あ、これかもしれない」と感じる。それがそのアニメーションにとっての「正解」で、存在していいものになる瞬間なんです。
そんな風に自分の中で「これが正解」と思えるものをずっと探し続けていたのが、若手の時代だったのかなと思います。
人の笑顔を見るとテンションが上がる!

ピーポーパニックを展示したときの写真

別コンテンツを社内で制作している様子




お金をいただく案件ではなくて、「うちの会社にはこういう技術がありますよ」とプロモーションするための作品だったのですが、結果的に文化庁メディア芸術祭のエンターテインメント部門で、審査委員会推薦作品に選ばれたのです。国に認められたということもあって、より自信につながった作品でした。
UFOが人を吸い込むというパニックゲームで、床に100インチぐらいのプロジェクターで大きく投影された街の映像の上に、釣り竿のような棒の先にUFO型のデバイスを取り付けてかざすと、建物や人が吸い込まれていくという仕掛けです。
仕組みを作っている段階から「これはおもしろいかも」とは思っていたのですが、果たして本当にウケるのかという不安もありました。でも実際に展示してみると、みんなが本当に楽しそうに遊んでくれて、とても嬉しかったです。


人を笑顔にできるなら、手段は漫才でも何でもよくて。たまたま自分の武器がプログラミングだった。だからそれを使って人を笑わせたい。自分の作ったもので笑ってくれる瞬間に立ち会った時、自分の奥の方から湧き出るような喜びやおもしろさがある。それが、仕事の原動力になっていると思います。
岡田さんに聞いた学生時代にすべきこと

趣味で制作した案件の印象的な場面をボクセル(ドット絵の3D版のようなもの)で作っていた時期があり、展示したことも
面倒だと口にしながらも、ちゃんとすることの意義


映像と組み合わせることでおもしろくなったり、デザインに動きをつけることで魅力が増したり、ホームページの情報にちょっとした動きを加えることで内容がより伝わりやすくなったり。アニメーションにもいろいろなバリエーションがあります。
いろいろやっているうちに「こっちもおもしろそう」「あっちもやってみたい」と、どんどん興味は広がります。けれど、自分の根底にあるものは変わらないので、きっと飽きないのだと思います。


たとえば、ある仕事を任されたとき、新しい知識を覚える必要があったとします。学ぶことは大変ですが、その知識を得たことで自分の作るものがより良くなります。さらに、そこで知った新しい言葉や技術が、他の仕事の理解につながることもある。少しずつ知識が増えていくと、新しい分野に興味がわいたり「これとこれを組み合わせたら、おもしろいものが作れるかも」と思えてきたりもします。
仕事を通じて「わからないままでは作れないし、わかっていた方が絶対いい」ということが実感として掴めてくるのかもしれません。そんな経験を繰り返していくうちに、勉強することが当たり前になり、どんどん楽しくなっていきました。




著名なクリエイターの方達の仕事を見ていると、やっぱり裏側ではとてつもない努力や手間がかかっている。ちゃんと作るから楽しいし、工夫するからおもしろいものができる。
でも、僕は手間を惜しまずちゃんとするのが苦手なところもあります。たとえば、脱いだ上着を床に置きっぱなしにして「あとで片付ければいいや」と後回しにしたくなる。だけど、もし納期の迫った仕事の案件が間近にあったとしたら、あとで上着を片付ける時間はない。そんな時、「時間がない」「面倒くさい」とこぼしながらも、ちゃんと上着をハンガーにかけるかどうか。
おそらく、同じことが仕事でも起こっていて、その一つひとつの判断がクオリティや完成度につながってくるんです。面倒だけど、やった方がいいに決まっている。
最近では「ちゃんとハンガーにかけた方がいいんじゃないか」と、時々自分の中の「仕事モードの自分」が、プライベートの自分に問いかけてくるようになりました。
何か一つでもやり切る、自分の感性を磨く


たとえ大学で学んでいたことと企業の分野が違っていても、「大学でこれだけ頑張ってきたなら、この会社でも頑張ってくれるだろう」と捉えてもらえるかもしれません。
ワットエバーのメンバーも、学んできた領域や経験はみんな違います。デザイナーでも、紙が専門だった人もいれば、空間やWEBの人もいます。他にもプロデューサー、コピーライター、マジシャンだった人もいる。それまで培った分野の知識や技術が武器となって、その会社の分野にハマることはあると思いますよ。


何か一つでも「自分がこれをやり切った」という自信や経験があること。将来やりたい仕事に直接関係していなくても、それはきっと武器になると思います。
たとえば、「この仕事にとても興味があります」というだけの人よりも、「いつもこんなイベントをやってきました!この分野がめっちゃ好きです。仕事はまだできないですけど、頑張って覚えます!」と言える人の方が魅力的に感じるものだと思います。


……でももしかしたら正直、エンジニア以外でもっと人を楽しませる方法を見つけたら、突然違うことを始めるかもしれません(笑)。
また、自分が携わったものでなくても、おもしろいコンテンツをきっかけに、学生さんや若いクリエイターが「何かを作りたい!」と思って、意欲的に創作に取り組んでくれるといいですよね。そうやって彼らから生まれた作品を、いつか自分が体験できたら、すごく素敵だなと思っています。

数年前、社内のスタッフが集まってご飯を食べたときの集合写真
(編集:横山 麻衣子/執筆:大島 爽)