この記事では、吉備国際大学の教授として、英語を通じて人との関わりを大切にする心を育てる池上 真由美(いけがみ まゆみ)さんの生き方に触れていきます!
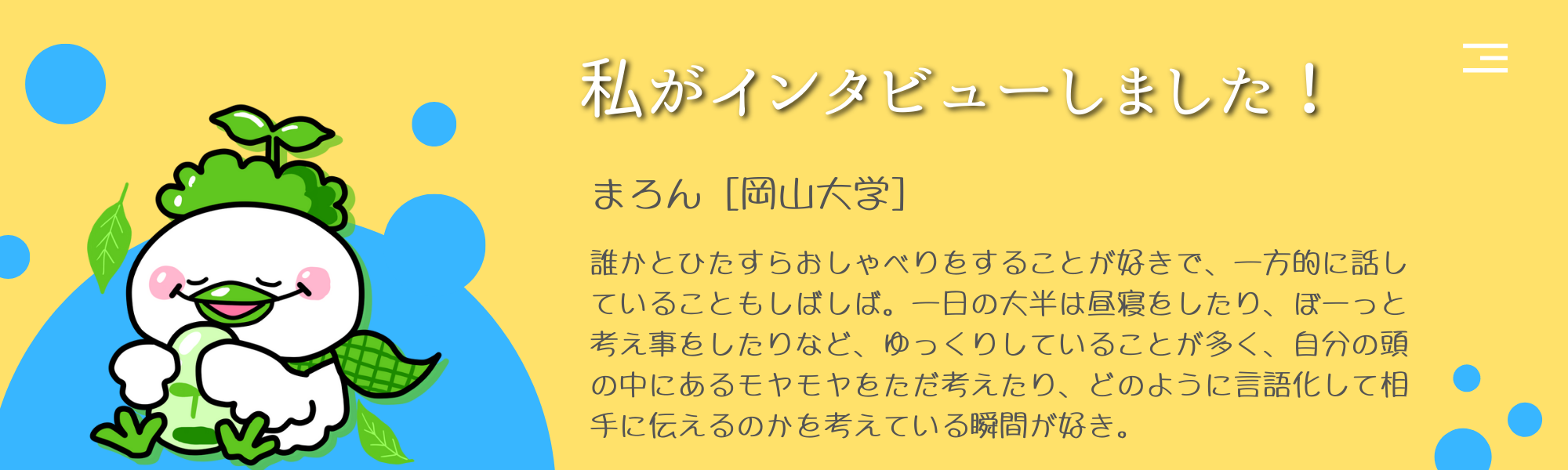
目次
池上さんのお仕事
英語は尊重の精神を育てることができる教科
──池上さんはどんなお仕事をされていますか?

──他の教科よりも人との関わりが英語は多いですよね。

人間を大切にする人を育てたい

──英語という手段で人間尊重の精神を育てることが、池上さんの大切にされている部分なんですね。

だから極端に言えば、英語はできなくてもいいんですよ。英語を一生懸命やろうっていう姿勢を身につけていれば。
──そのような英語の魅力をどの様に中学生に伝えられていますか?

ただ、これを言葉で言うだけでは伝わらないから、授業の中で体験しながら伝えていきます。勉強は基本一人でするものですけど、授業はみんなで作るようにしていましたね。英語の授業なんだけど、道徳の授業だと思って作っていました。
アメリカと日本で感じた教育の差


海外の学校はとにかく小さい頃から自分の意見を持って、それを表現させる訓練を受けてきています。でも日本の子どもって、表現する訓練を受ける機会が少ない。
──小・中学校でディベートなどのディスカッションをする機会ってほどんどないですよね。

実際に大学での授業を見てると、大体簡単にまとめちゃって、議論を深めていかないんだよね。だからすぐ話し合いも終わるし、浅い話し合いで終わっちゃってるんだよね。
──生徒が主体的に考えたり、発言し、行動するといった部分の差を感じられたんですね。池上さんが考えられている、これからの教育の理想はなんですか?

やっぱり教育は先生から与えるっていう一方的なものじゃなくて、学ぶ側がこれをやりたい、こんなふうに追求していきたい、そういう主体性を持てるような教育をこれからもっともっとやっていかないといけないと思っています。
池上さんのこれまで
教育に進むきっかけとなった大学生活

──池上さんが教員を目指したきっかけって何ですか?

最初は絶対教員になるつもりはなくて、英語を使って仕事しようと思っていました。その考えがコロっと変わったのが教育実習ですね。大学3年生の時に行った教育実習で、180度変わりましたね。もう絶対に先生になりたい!って。
──「なりたくない」から、「なりたい」に変わったんですね。

そもそもなんで教員になりたくないと思ってたかというと、中学3年生の時の担任の先生が「お前ら絶対教員にはなるな。こんな大変な仕事はないぞ。」って言うんです。それをすごく真に受けて、「そうなんだ、やっぱ大変なんだ。」って思って、絶対に教員にならないと思っていたんです。
──そこから教育実習に行って変わられたんですね。教育実習のどこが魅力的だったんですか?
授業中は全然反応しなかったような子とか、真面目にやってくれなかった子が、「良い先生になってください!頑張ってください!」って書いてて。それをもらうと、もうダメで笑。「なるしかないかー!」と、本当に180度コロッと変わって。絶対教員になろうって思いましたね。
──子どもたちに落とされた訳ですね(笑)
小学校・中学校を経験した教員生活


1年間、長野県で中学校の教員をした後に、岡山県に来て中学校の講師をしました。その後も岡山県の教員採用試験にチャレンジしてたんだけど、中学校英語の教員の採用がほぼないっていう状態だったので、とりあえず小学校の先生になろうと考えました。小学校の教員になってから、人事交流の制度で中学校に異動しようという長期計画に変更したんです。
──小学校の教員を経験された後に、中学校の教員になられたんですか?

中学校の教員になれたのは、私が教員になって13年目ですかね。小学校を2校経験した後に、やっと本当にやりたい中学校の英語に戻ってこれたんです。
──それからは中学校の教員として英語を教えてこられたんですか?

学校の教壇をおりてから今まで


だから、小学校英語と中学校英語の両方について語れるのは、どちらも経験した私しかいないかなと思っていましたね。
──小・中どちらの現場も長年経験されている先生って珍しいですよね。

当時は、中学校の教員になるまでの13年間は回り道かなと思ったんだけど、最終的にはいい経験だったなと思いますね。
──当時は回り道だと感じても、今改めて振り返ると池上さんにとって大切な時間だったんですね。


(編集:森分志学)


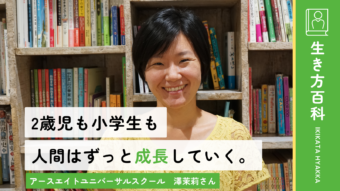

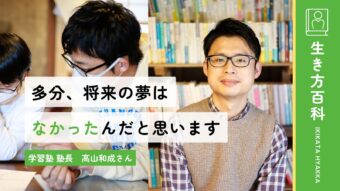


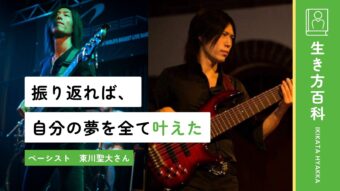
英語が良い教科だなと思うのは、一人では学べないところなんです。必ず相手がいて、人と繋がるときに必要になるツールですよね。だから英語という教科を通して、人を好きになる・人を大切にする・自分を大切にする、そういう人間尊重の精神を育てることができる教科だなと思ったんですよ。