「自分で考えて自分で決める」が経験できる環境づくりをおこなう「ボブ」こと、高瀬敦之(たかせあつし)さん。実は元プロサッカー選手で、転身して教育活動に関わるように。この記事では、そんなボブさんからお話を伺います。
目次
現在の高瀬さんのお仕事
サッカー選手から教育活動者に
——高瀬さんは何をしている人ですか?
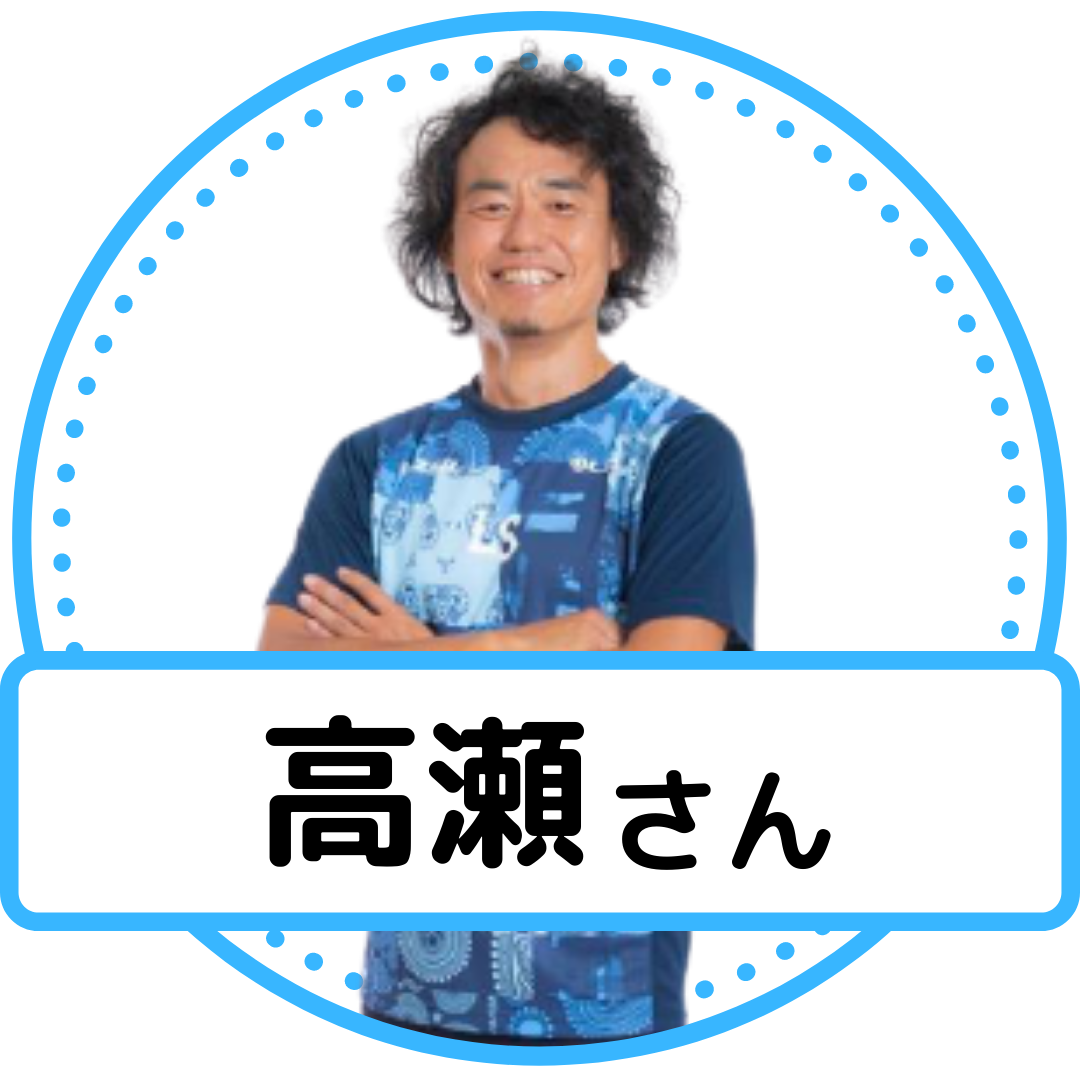
——「ボブ」というニックネームの由来は?
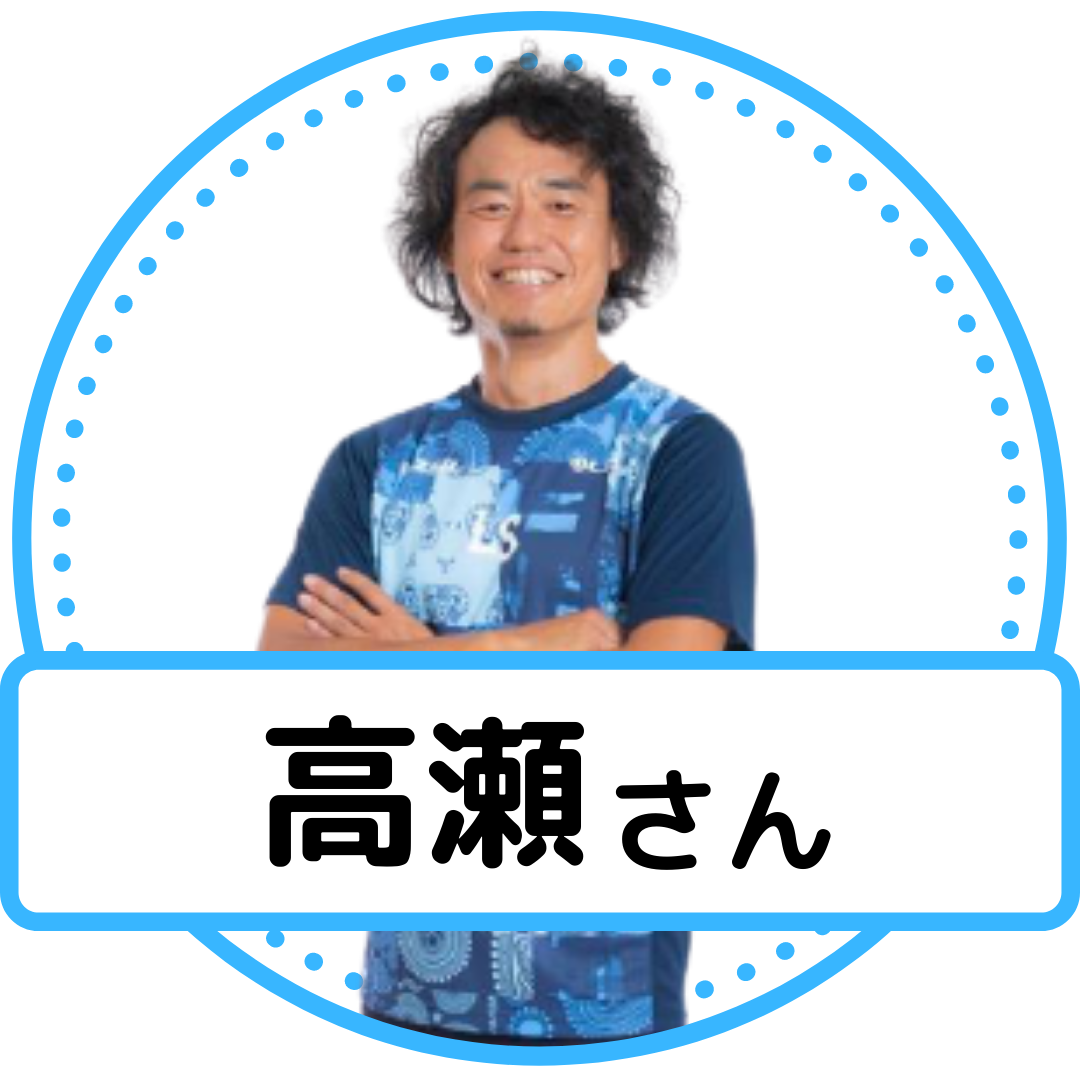
教育の現場では、子どもたちから「ボブ」と呼ばれています。垣根を無くすと言いますか、先生やコーチだと思ってほしくない。先生やコーチとして関わると、どうしても上下関係ができてしまって、指導になってしまいます。自分で考えて選択してほしいので、指導はしたくないんです。

——今までで大変だったことは何ですか?
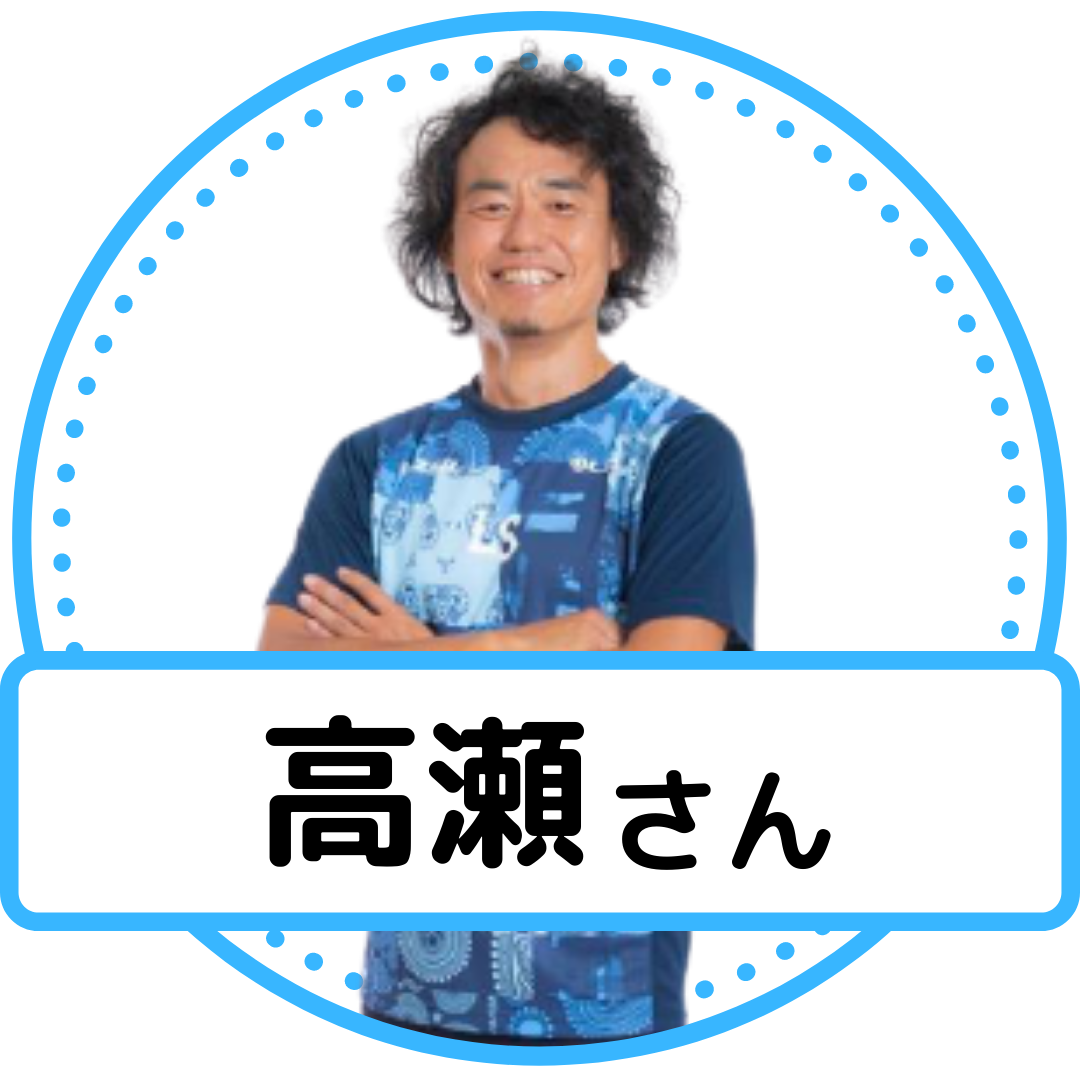
大学3年生の時に大好きな彼女と失恋をして。気持ちを癒したくて、イタリアにサッカーをしに行くことにしたんです。
チームメイトには、チームが大切な時期に行くなと止められたのですが、一度決めたことなので、譲れませんでした。常に「決める」と言うことをしてしまうので、人に伝えたときにはもう揺るがないです。
高瀬さんの脳内
脳内グラフとは、高瀬さんの頭の中を垣間見て、その割合を数値化したもの。どんなことを日々考えているのか聞いてみたいと思います。

どれだけ人に喜んでもらえるか 100%
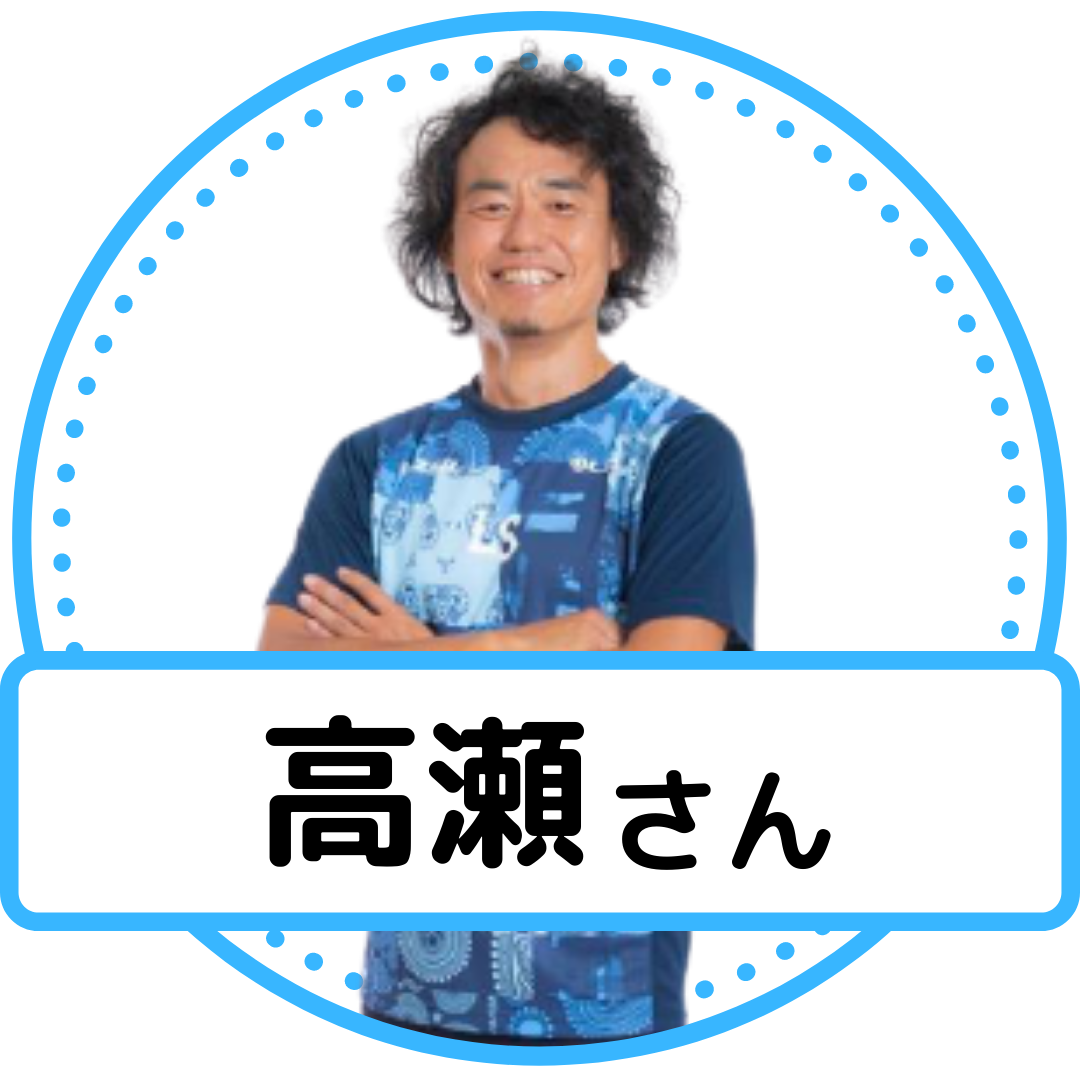
例えば、無人島生活を行う島学では「どうやったら子どもたちが楽しめるか」を一番に考えています。主役は子どもたちなので、どうやったら子どもたちが動きやすいかを常に考えていますね。

高瀬さんのこれまで
第1章 「ふつう」じゃなくていい
小学生の頃、母親が体調を崩して家から出ていったときに、「自分のコトは、自分でキメる」ことを誓いました。「ふつうの家庭じゃなくなった」と父親から言われたとき、その言葉の意味とは裏腹に「ふつうじゃなくていいんだ」と嬉しさも感じたことを覚えています。長男だから、これまでの情報も少なく、生きていく道は自分で体験して切り開いていくしかない中、ふつうじゃなくなったと言われたことで、「ふつうの道から外れてもいいんだ」と思えて。
何だか塗り絵みたいだなと思っていて。間違った色で塗ってもOKだし、ふつうじゃなくていいのが一つの選択肢というか。思った通りに表現すればいいんだって、父親に言われた気がして。その時期から、自分で考えて、選択して、行動する癖がついたなと思います。
第2章 1人3役
小学生の頃からサッカーをやっていて、中学校でもサッカー部に入部しました。3年生になってキャプテンをやることになりましたが、部活動の監督がいなかったんですよね。なので、自分が監督の役割もしつつ、キャプテンの役割もしつつ、普段は同級生として接する、みたいに1人で3役しないといけないことになって…
その立場で練習メニューを提示したりしていると、「あいつ、なんか偉そうだな」ってなるんです。その結果、サッカー部の同級生から嫌われてしまって、孤立状態になってしまいました。寂しかったし、悩みました。
でも、悩んだのは一瞬で、「サッカー部の人と仲良くできないんなら、他の部活の人と仲良くすればいいな」と切り替えて他の部活の友達と仲良くしていました。切り替えてはいても、悔しい気持ちはどこかにずっとありました。高校を決める時には、さすがにサッカー部の同級生とは別の高校に進学したいなと思って、地元から離れた高校に決めました。
第3章 サッカーは仕事になると知る
サッカーを仕事にしようと思ったのが、高校1年生の時でした。それまでは、なんとなくサッカー部に所属して、楽しくサッカーをしていただけだったんですが、僕が高校1年生のときに、Jリーグができました。
サッカーを仕事にしていいんだと知って、本気でJリーガーを目指し始めました。サッカーの強豪校に入学して、高校3年生のときにはレギュラーにも入れました。すごく自信になりました。
第4章 結果よりも過程が楽しい
大学でも、プロを目指し続けていました。当時、岡山にはプロサッカーチームが無かったので、関西の大学に進学しました。その間ずっとプロテストを受け続けていたんですが、大学4年生になってもオファーが来なくて。厳しい世界です。でも、結果が出たときよりも、過程が楽しいことを知っているので、頑張れました。
今の教育の活動も同じだと思っています。教育って過程そのものだと思っていて、結果が見えないじゃないですか。そういう世界で楽しめるのは、きっと過程を楽しめる性格だからだと思います。

第5章 教育とビジネス、違和感。
岡山にプロサッカーチームができたのをきっかけに、岡山に帰ってきて、目標だったプロサッカー選手として活動することになりました。
プロのサッカーチームに所属したらサッカースクールを運営する決まりになっているんですが、そうした普及活動もビジネスのひとつですよね。子どもの夢がビジネスに使われてしまうことに違和感を覚えて…
第6章 独立
その違和感を覚えた時期に、サッカースクール「すまいるキッズ」を立ち上げました。このスクールでは、サッカーを教えることはしないんです。「小さい頃からサッカーって教えたらいけないな」という逆の発想に至って。
自分のサッカー人生を振り返ったとき、「先生」っていなかったなと気づいたんです。人に言われてやるより、自分がやりたかったからやってきた。その経験があるから今の自分があるなと思っています。子どもたちには自ら考えて行動できる人になってほしいので、そういう環境づくりを心がけています。

(編集:森分志学)

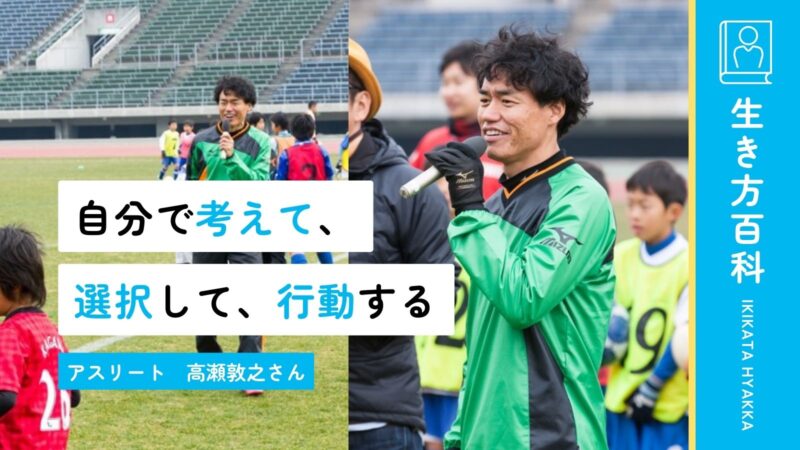



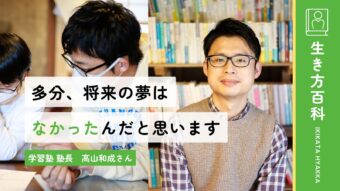
今は、子どもたちが週末の3日間、無人島で生活する「島学」に力を入れています。無人島生活を通して、自分で考えて自分で決める力を育むことのできる環境づくりをしています。
学びを自分でつくり出す時代だからこそ、自分で考えて行動しなければいけないと思っています。その力は、座学だけでは身に付きません。知りたいこと・やりたいことを見つけて、「やってみてどうだっただろう」「次はどんなことを学ぼう」、そんなふうに自分だけの学びを探し続けられるようになる、実践型の学び場をつくっています。