皆さんの食卓に、ほぼ毎日出ているのではないかというお米。農家の人たちが稲を刈り取ったあと、もみという固い殻を割る作業があります。そこで活躍する農業機械の籾摺り機(もみすりき)の心臓部である「もみすりロール」を製造し、国内No.1シェアを誇っている企業が株式会社水内ゴムです。
岡山学芸館高校の「課題研究連続講座」として、高校生が水内ゴムで働く社会人とインタビューを行いました。この記事では、代表取締役社長の水内雄一さんと営業担当の國米成之さんからお伺いしたお話を紹介します。
目次
農業機械の籾摺り機の心臓部を製造する
日本の食文化を支えるゴム製品


もみすりとはお米に関する作業で、お米を食べられる状態にするために、稲を刈り取ったあと、もみという固い殻を割る作業を指します。割ったばかりの状態だと玄米となり、玄米の表面を削ると白米になるんです。玄米にするときに使われるのがもみすりロール。皆さんが食べるお米の約半分は、水内ゴムのもみすりロールを通ってきたお米と言えるんですよ。

籾摺りロール工場


食品用シリコン型
メーカーさんと、型に線を1本入れるか入れないかといった試行錯誤をしながら、オリジナルの型を作ることもあります。お客様の要望を聞きながら、思いを「型」という形にしています。
困りごとの解決策が挑戦へのあしがかり
――もみすりロールからお菓子の型へと、製品の幅が広がっていますよね。新しいことに挑戦するきっかけは何でしょうか?

――どの会社でも営業と聞きますが、営業って具体的に何をするんですか?

営業担当は、お客様がどんな問題を抱えていて、何を欲しているのかを聞き出し、「水内ゴムの製品で問題解決しませんか。すごく楽になりますよ」と提案をするんです。水内ゴムの場合は、取引先に直接トラックで届けることもあります。

――営業とは、会社とお客様をつなぐ役割なんですね。ホームランドームはどういうきっかけで運営を始めたんですか?

私の父が水内ゴムの社長だったときに、「空き地をバッティングセンターにしたらおもしろそうだな」と思ったのがきっかけだったそうです。ホームランドームの1号店は、水内ゴムの使っていない工場予定地でした。1号店が人気になり、岡山県周辺で少しずつ広げていったんです。
――社内では旅行やイベントはあるんですか?

バーベキューや飲み会を社員のコミュニケーションのツールにしてもらおうと、食事会の費用を会社がある程度負担していました。今は食事会の回数が少なくなっていますが、コロナが落ち着いてきたら少しずつ増やしていけたらと思っています。
企業理念は従業員の幸せの追求と社会貢献

理念について、学校の授業で聞くことは少ないかもしれませんが、僕のなかで理念は重要だと思っています。もし会社に行ったり学校を選んだりするときは、気にしてみてください。
――「全従業員を大切に」という理念がどういう経緯で生まれたのか詳しく聞きたいです。

私も社長になった当初は、「企業理念はあってもなくてもいいかな」と思っていました。けれど、社長同士の勉強会のような場で経営について学ぶなかで、企業理念の重要性に気づきました。
ちょうど、水内ゴムが100周年になるというタイミングでもありました。お客様はもちろん大切だけれど、やはり従業員があっての会社。従業員が幸せだからこそ、お客様にいろいろな商品やサービスを提供できる。そう思って、水内ゴムは従業員を幸せにする会社であり、そのうえで社会貢献をしていく会社であることを企業理念にしたんです。
企業理念を掲げてからは、機会があるたびに社員に伝えるようにしています。学校に校風があるように、会社にも会社ごとの雰囲気があるんです。「うちの会社はこういう会社ですよ」ということを文章にしたのが理念だと思っています。会社を選ぶときは、「自分と合うな」「自分が幸せになれるな」と感じる会社を探してみてほしいです。
――全従業員の幸せを意識して取り組んでいることはありますか?

自分が何かを判断するとき、企業が続くことを重視していた時期もありました。ですが、今は従業員がなるべく幸せになる選択をするようにしています。

創業100周年記念式典
お二人の学生時代エピソード
岡山から出ることで視野と人間関係が広がった
――水内さんはなぜ東京大学を目指したんですか?

――何かきっかけあったんですか?

東京大学を目指すことを決めたんですが、僕の通っていた高校から東京大学に受かるのは1年に1人いるかどうかくらいだったので、先生に受験することを猛反対されました。「やめろ。受けたら落ちる」「他の大学はどうだ」と言われたけど「いや、頑張ります」と言い張っていましたね。
――そんな状況で、本当に東京大学に入学したことがかっこいいです。憧れって強いエネルギーになるんですね。

――大学時代にアメリカにも行かれたんですよね!なぜアメリカに行こうと思ったんですか?

僕が学生だった時代も、現在と変わらずアメリカ経済は強くて、「その文化とかに触れてみたい」「英語を聞いて話せるようになりたい」という気持ちがあったんです。
大学4年生のときに休学して、アメリカに留学しました。アメリカと日本って、文化が全然違うんです。僕の当たり前が全然当たり前じゃなくて驚きました。たとえば、日本の大学の授業は、教授の話を聞くだけで終わることが多いですが、アメリカの学生は手を挙げて「先生、ここがわかんないんだけど」とどんどん質問する。さっきまで寝ていたような学生も質問をするんですよ。日本だと寝ていたことをまず怒られるんじゃないかと思いますが、アメリカの教授は「いい質問だね。もう1回説明しよう」といって説明していました。
他にも、言葉の壁があったり、冬が寒すぎたり、日本と違うことはたくさんありました。日本や岡山のなかだけで育っていると、そこが基準になる。岡山から東京に行くと、東京と岡山とを比較できるし、アメリカに行くとアメリカと日本とを比較できるようになります。

――國米さんのお話も伺いたいです。大学を選んだ理由やきっかけはなんですか?

――なぜ岡山に戻ってこようと決めていたんですか?

――素敵な理由ですね!
今も活きる学生時代の経験や出会い

――お二人とも県外や国外に行って、いろんな世界を見て、いろんな人と出会ったと思います。その経験から仕事や仕事以外で今に活きていると思うことはありますか?

あと、東京に知り合いが増えました。自分が東京に行くときに短い時間でも会える人がいたり、東京のことを教えてもらえる頼れる存在がいたりするのは、ありがたいです。反対に、東京から岡山に来る人がいれば岡山のまちを紹介することができる。岡山以外の場所で知り合いが増えたことで、仕事でもプライベートでも活きるつながりができました。

大学時代の出会いという意味では、当時所属していたテニスサークルで仲がいいメンバーのうちの1人が起業して、最終的に会社を上場させたんです。最近もニュースで取り上げられていました。その人には数年に1度ぐらいのスパンで会うんですが、会うたびに刺激を受けています。あいつも頑張っているから俺も頑張らなきゃなって。
――友達はたくさんいるほうがいいですか?

――なるほど。お二人ともありがとうございました!
(編集:森分志学)


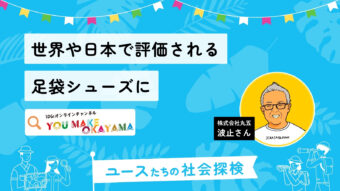
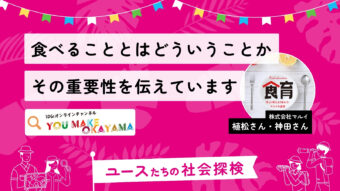
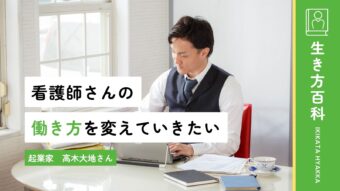

水内ゴムはホームランドームを運営している会社ですが、会社の名前のとおり、ゴム製品の製造もしています。水内ゴムの事業は大きく分けると、「もみすりロール事業」「工業用ゴム部品事業」「バッティングセンター事業」の3つです。