今回は、アーク訪問看護ステーションの富永芽生(とみながめい)さんをご紹介。
幼い頃から看護師になるために突き進んできた富永さん。初めは病院に勤務する看護師でしたが、現在は職場を変え、患者さんの自宅に訪問してケアをしています。訪問看護をおこなううえで富永さんが大切にしていることや、これまで歩んできた道はどのようなだったのでしょうか。
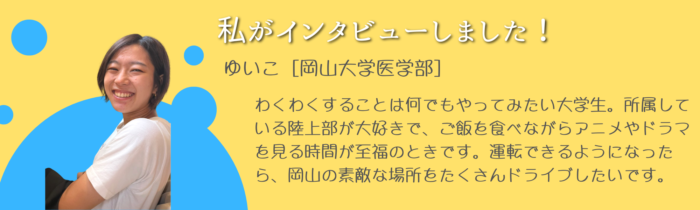
目次
富永さんのお仕事
患者さんの自宅に訪問する看護師
――富永さんが取り組まれている「訪問看護」とはどのようなお仕事ですか?

――利用者さんにはどのように接しているのですか?
状況次第ですが明るく朗らかにいられるようにということも意識しています。また、利用者様一人ひとり、性格はもちろん、体の状態が違うんです。「この人はこんなキャラクターだから、こうしたらいいんじゃないかな」と考えながら、お試ししてみようとすることがあります。 「その方の生活リズムだと、こういうことが起きそうだから、事前に〇〇をておいた方がいいかも。」といったことを考えるのが好きなんです。それが一人ひとりに寄り添った看護だと思っていて、一番意識しています。 でも、失敗もたくさんあります。

――どんな失敗ですか?

あと、小さいインシデントはよく書いています。
――インシデントとは?

たとえば、鼻から入れている経鼻栄養チューブを入れている患者様が誤ってチューブを抜いてしまった場合、インシデントに該当します。病院勤務をしていたときはよくありました。小児科にいたときは、子どもが栄養チューブを抜いてしまうと毎回インシデントレポートを書いていましたね。
「どうしたらそれが起きなかったのか」という原因や対策を追求するために、インシデントがあります。
――失敗してしまったときの乗り越え方は何かありますか?


明るい笑顔で思いをくみ取り、すり合わせる
――富永さんがお仕事で大切にされていることは何ですか?

――素敵ですね!笑顔でいるなかでも、難しさや葛藤を感じる場面はありますか?
「病院だったら」という視点は、そもそもお家での生活が前提ではなくなってしまう。利用者の思いや生活基準に合わせたうえで、最大限できることを考えることが難しくなるんです。「病院だったら」とは考えずに、利用者の気持ちに合わせていくことを考えます。 たとえば、「利用者が食べたいと思っているものを制限したほうが回復する」というようなケース。糖尿病の方にとって、食生活や内服の管理は大事ですが、生活習慣を変えるのは難しいんです。どうすり合わせていくかを考えるときに、あまりにも看護師の視点になりすぎると、利用者との信頼関係が崩れて、関わることが難しくなるので、いつも葛藤するんです。
――葛藤したときに、何か心がけていることはありますか?
利用者の方の思いとして「こうしたいんだな」とわかったら、その望みはなるべく実現できるように取り計らいながら「じゃあこれも頑張りましょうね」とすり合わせていきます。在宅では「そう思った理由は何ですか」と聞いていくことが多いですね。

課題は人材育成の仕組みづくり
――利用者との関係性づくりが大切なのですね。訪問看護全体についても聞かせてください。業界での課題はありますか?
病院には、新卒1年目から基礎的な研修やカリキュラムがあります。技術面で学べる機会がたくさんあり、訪問看護を担当することになってもスムーズに移行しやすいです。一方、訪問看護ステーションには、新卒1年目から勤務する方はとても少なくて、技術に関する研修がほとんどない。 経験者が務めることが多かった業界ですが、最近はありがたいことに新人の方が応募してくれることが増えてきました。しかし、今はまだ研修の機会がなかなか作れなくて。未来の人材を育成する機会が少ないことが、大きな課題だと感じています。
――人材育成に関して、今取り組まれていることはあるでしょうか?

――訪問看護の業界では、人手不足が問題になっていると耳にしました。その解決にも繋がりそうですね。

富永さんのこれまで
4歳で出会った看護師が将来の夢に

――富永さんの人生の歩みを教えていただけますか?

――訪問看護の世界に飛び込まれたきっかけは何ですか?
わたし自身、小さい子のお世話が好きで、保育園でも年下の子のお世話をしてたんですよ。中学生くらいから「わたしは小児科の看護師になりたい」という強く思うようになっていました。高校も「大学は看護学科に行くんだ」という目標を持って勉強をし、大学では子どもの支援について学びつつ、看護師になることを一心に考えていました。 ――目標は達成されたんですね! すると、夜勤がある仕事だと娘が幼い間にそばにいられないという悩みが出てきてしまったんです。でも、看護師の仕事はとても好きなので辞めたくはない。似たような仕事を探していたら、訪問看護は子どもがいても仕事ができることを知りました。「自分が幼い頃に見ていた訪問看護の看護師はこれか。やってみよう」と思って、飛び込んだんです。


学生時代の経験や人間関係が今に繋がっている
――そうだったのですね。学生時代のことを伺いたいのですが、高校時代にこれをしていて良かったと思うことはありますか?

――参加してどうでしたか?
一方で、そんななかでもとても楽しそうに過ごしている子どもたちの姿を見て、どんな境遇でもキラキラしている姿に感動しました。素敵な経験をさせてもらって、視野が広がりました。
――その経験に今のお仕事に活きていますか?

――高校時代の経験が今に繋がっているのですね!今、高校生の富永さんに声をかけるとしたらどんなふうに声をかけますか。
また、今の中高生の皆さんには、時間を大切にしてほしいなと思います。1日1日を楽しく、友達と過ごせる時間は貴重だし、高校の3年間は戻ってこないじゃないですか。わたしは大学でできた友達との付き合いが長いんですけど、高校の友達が一生付き合う友達になる人もいると思います。
高校生の間にやったことって、未来の自分に繋がっているなと思うんですよ。なるべくチャレンジや失敗をたくさんしてほしいなと思います。

(編集:森分志学)



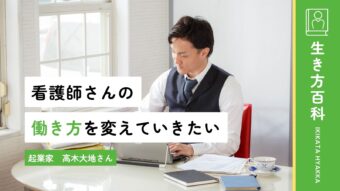
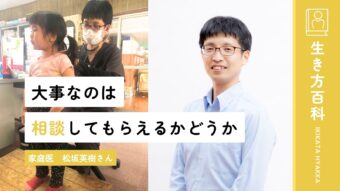


たとえば、ストーマ(人工肛門)といって、消化器系のトラブルがある患者様の腸をお腹の外に出して新しい排泄の出口を作ることがあります。そういった場合、皮膚トラブルを起こしやすかったり、ストーマ用の装具を管理する必要があります。そうした方のお家に看護師が訪問してケアをすることで皮膚トラブルを防いだり、状態の報告を病院側へして早めの受診を促したりすることができます。
がんの末期の方が「病院はよりも家に帰って最期を過ごしたい。」とおっしゃる場合、在宅診療の医師と連携して、お家で痛みを取りながら最期まで過ごせるように、家族様を含めてサポートをしたりもしています。