交通インフラやライフライン、防災施設など、私たちの暮らしを安全・安心に支える縁の下の力持ちのような企業があります。どのようにして、私たちの「当たり前の生活」を支えているのか、総合建設コンサルタント株式会社ウエスコさんに詳しく伺いました。
目次
交通インフラやライフラインを支える
道路・鉄道・橋・港湾・空港・電気・ガス・水道も!
――まずはどんな事業をされているのかについて教えてください!

――どんな依頼が多いのですか?


河川や谷、池、海等をまたぐ橋梁では、橋梁点検車で点検する
――知らないうちに、生活の中にウエスコさんの技術が散りばめられているのですね。
交通工学という研究分野があり、体系化されたノウハウが存在していますが、地域によって状況が異なるため、地域ごとの対応が必要となります。交通工学のマニュアルをもとに交通状況を把握し、どう展開していくのかと考えることが醍醐味です。
――ちなみに、仕事の依頼はどのように来るのでしょう?

自然環境分野の強みを活かして水族館も運営
――「未来に残す自然との共生社会」という企業理念が気になりました。理念に基づいてどんなことをされていますか?

――水族館も運営されていると伺いました。


守るべき環境を調べ解明するため、精度の高い調査・解析を実施

渋滞を解消する交通計画課・赤池さん
入社には大工の父の影響が
――入社のきっかけを教えてください。
さらに、父親が大工で家を作っていて、子どものころから現場に連れて行ってもらっていました。モノづくりを仕事にしたかったので、大学では土木系の環境デザイン学科を専攻しましたが、現場で力仕事をするのは向いていないと感じたため、建設コンサルタント会社を選びました。
――入社の決め手は何だったんですか?

――どの部署に配属されたのですか?

職業病になるくらい交通渋滞について考える
――仕事のやりがいを教えてください!
ただ、職業病でしょうか。運転中に渋滞が起こったら、なぜ起こったのか、もっと効率的に解消できる方法はないかなど、考えてしまいますね。そういうことも楽しいです。
――どんな渋滞対策をされているのですか?
例えば、右折の車線が足りていない場合は、右折車線を延ばすことが考えられます。土地を買わなければいけない対策や、土地を買わずに簡易に対策できる方法を検討します。対策案が決まったら、設計担当が設計をし、例えば右折車線を入れて歩道が減る、歩道から外側にどれだけ土地を買わないといけないか設計をします。自治体で対策内容が決まったら、工事会社に発注し、工事が行われ、渋滞が緩和される流れとなります。
――なんだかとても難しそうです…!

3~5年経験を積んで一人前
――働きやすさはいかがですか?

――仕事を進めるなかで大変なことはありますか?
関係各所のバランスを取りながら最適解を提供するために、調整を含めたコンサルティングが必要になります。地元からの反対というニュースを目にしますが、事前調整が不十分だとこういうことが起きます。調整の窓口は基本的に自治体が行いますが、専門的なことについては私たちが代わりに説明や対応をすることもあります。経験や知識が必要になるため、土木の業界は経験工学と呼ばれることがありますね。3年~5年経験を積んで、一人前の業界です。
それで社会が良くなる?と自らに問う
――仕事をするうえで、大切にしていることを教えてください。
インフラを維持していくためには、将来の子どもたちの税金も使われる可能性があるので、本当に必要なものかどうかを考えることが大切です。効率的に都市を運営するというコンパクトシティ(都市を小さくして、無駄な開発やインフラ整備のコストを抑える)という考え方も注目されています。いかに賢く都市を運営するかという視点もあるので、やはり「それで、社会が良くなる?」ということは頭に入れて仕事をしています。
ウエスコと赤池さんの目指したい未来
――まずは赤池さんご自身の目指すところを教えてください。

――興味深いです。具体的にどんな取り組みになるんでしょうか?

――さいごに、ウエスコさんが目指したい未来について教えてください。
今は主に西日本を中心に事業を展開していますが、企業として成長すべく、関東や中部地方にも進出しています。さらに、最近では海外展開も始まっています。
――赤池さん、今日はありがとうございました!
(編集:横山 麻衣子)





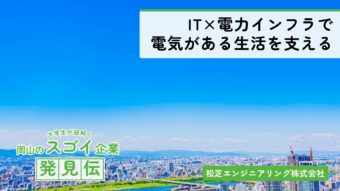
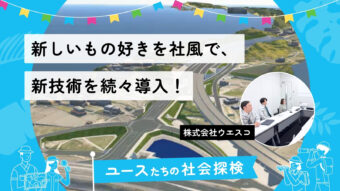

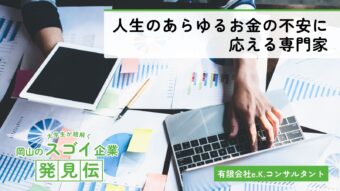
例えば、道路やトンネルや橋の設計、水の流れを分析した河川の浸水シミュレーションなどを行っています。また、渋滞対策など交通の円滑化を図るため、信号や交通網の計画を行っています。上下水道や公園の設計や老朽化対策など、生活に密着した様々なプロジェクトを行っています。